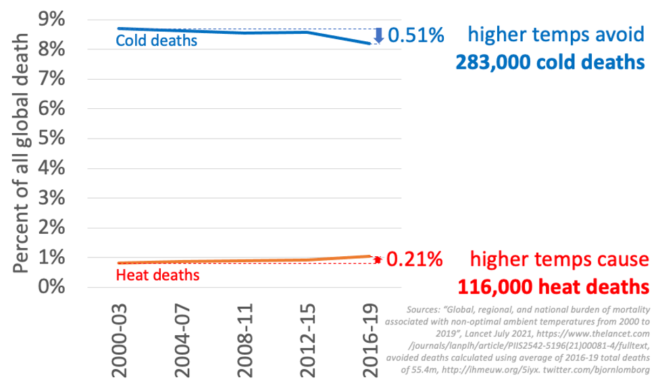生成AIがバブルの様相を呈しているが、それはしょせん事務員を代替する機械学習であり、いくらビッグデータを集積してもイノベーションは生まれない。ポパーは経験を帰納して科学理論が生まれるという「帰納主義」を否定し、新しい理論を生むのは経験ではなく仮説だとした。
タレブはポパーの否定的知識(subtractive knowledge)を高く評価し、イノベーションに必要なのはビッグデータではなく、既存の常識を否定することだという。そういう自由な学問が初めて生まれたのは、古代ギリシャだった。
ソフィストと呼ばれるソクラテス以前の自然哲学者は互いを自由に批判し、タレスやアナクシマンドロスは弟子が師匠を批判することを奨励した、とポパーは書いている。彼らは原子論やピタゴラスの定理などの自然哲学を生んだ。クセノパネスはこう書いている。
神が万物を明らかにするのではない
われわれが自分の探究によって
時とともに学び、知識を深めてゆくのだ
しかし古代ギリシャの自然哲学は、ローマ帝国に継承されなかった。それがイスラム圏を通じて中世ヨーロッパに伝えられ、自然科学を生んだのは、その1700年も後だった。なぜかくも長い間、古代ギリシャのイノベーションは忘れられたのだろうか。
続きは2月5日(月)朝7時に配信する池田信夫ブログマガジンで(初月無料)
タレブはポパーの否定的知識(subtractive knowledge)を高く評価し、イノベーションに必要なのはビッグデータではなく、既存の常識を否定することだという。そういう自由な学問が初めて生まれたのは、古代ギリシャだった。
ソフィストと呼ばれるソクラテス以前の自然哲学者は互いを自由に批判し、タレスやアナクシマンドロスは弟子が師匠を批判することを奨励した、とポパーは書いている。彼らは原子論やピタゴラスの定理などの自然哲学を生んだ。クセノパネスはこう書いている。
神が万物を明らかにするのではない
われわれが自分の探究によって
時とともに学び、知識を深めてゆくのだ
しかし古代ギリシャの自然哲学は、ローマ帝国に継承されなかった。それがイスラム圏を通じて中世ヨーロッパに伝えられ、自然科学を生んだのは、その1700年も後だった。なぜかくも長い間、古代ギリシャのイノベーションは忘れられたのだろうか。
続きは2月5日(月)朝7時に配信する池田信夫ブログマガジンで(初月無料)