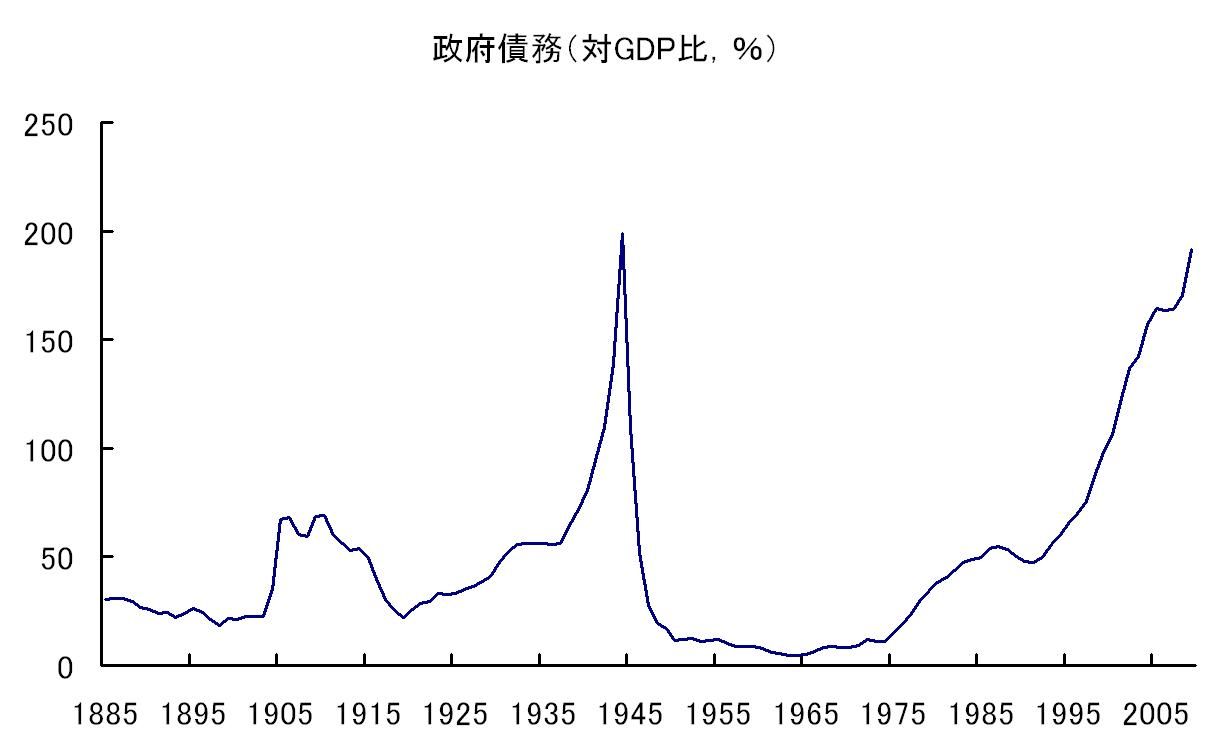日本のサービス産業の効率が低いことは周知の事実だが、教育サービス(特に高等教育)はその中でも最低の部類だろう。私立大学の過半数が定員割れで、中国人留学生で定員を埋めている状態だ。一時、文科省が「大学院重点化」によって乱造した大学院大学も、ほとんどが定員割れで「学歴ロンダリング」の温床になっている。
こういう状況について何度も改革が試みられたが、ほとんど改善されていない。その根本的な原因は、企業システムにある。拙著(第5章)でも書いたように、日本の企業のガバナンスは資本主義の原則である所有権(ownership)による支配ではなく、長期的関係にもとづいた会員権(membership)による支配だから、大事なのは組織に忠実で協調性の高いことで、専門的技能は必要ないのだ。
前にも書いたように、日本の大学はシグナリングの装置だから、その役割は入試のとき終わっている。重要なのは「東大卒」の学歴ではなく「東大入学」の能力だから、4年間は遊んでいてもかまわないし、大学の成績も重視されない。仕事は徒弟修行によってOJTで覚えるので、それを習得する文脈的技能が高ければよい。あのつまらない受験勉強を耐えて東大に入った学生は、どんなつまらない仕事も我慢し、上司の求める答を出す忠実な社員になるというシグナルを出しているのである。
だから企業システムを変えないで、教育システムを変えることはできない。企業が汎用サラリーマンを求めているのに、必要もない大学院卒を増やしても、労働市場での価値は上がらない。長期雇用・年功序列システムの特長は、需要の変化に対応して多くの部門に配置転換できる柔軟性なので、へたに博士号をとったりして「専門バカ」になると、つぶしがきかなくて使いにくい。
こうした教育システムが行き詰まっているのは、日本企業の行き詰まりに対応している。かつては市場の変化には配置転換や出向・転籍で対応できたが、情報革命とグローバル化によって変化が急速になり、競争が激しくなると、高度に専門化された企業による水平分業が起こり、サラリーマンでは対抗できなくなる。ところが企業の人事システムは昔のままだから、専門的な判断力のない調整型の経営者が組織内のコンセンサスで経営戦略を決めて失敗を繰り返す。
逆にいうと、学生が専門的技能を生かすには、柔軟な労働市場が必要だ。そのためには、企業が現在のような長期的関係に依存した閉鎖的な共同体ではなく、資本市場で所有権を移転して柔軟に組み替えるモジュールになる必要がある。これはゲーム理論でいうと、繰り返しゲームから戦略的ゲームへの転換である。つまり
問題は、1のシステムが長期的に維持可能かどうかということだ。私は、グローバル化の進む世界経済の中でこういうシステムを死守することは、玉砕戦法に等しいと思う。だとすれば、好むと好まざるとにかかわらず、普通の資本主義に移行するしかない。異なる均衡への「パラダイム転換」にともなうリスクや社会的コストはかなり大きいが、それを先送りした結果が「失われた20年」の長期停滞である。
だから教育改革も、産業構造の改革の一環として進めないと失敗を繰り返すだろう。大学進学率が50%を超えた現状では、もう大学はアカデミズムではないので、大部分の私立大学は専門学校と同じように労働市場で即戦力になる人的資源を養成すべきだ。それが離職者の受け皿になれば、柔軟な労働市場を実現して企業システムの改革にもつながるだろう。この意味で、NIRAも提言するように、文科省が経産省や厚労省と連携して、産業政策として大学教育を再建する必要がある。
こういう状況について何度も改革が試みられたが、ほとんど改善されていない。その根本的な原因は、企業システムにある。拙著(第5章)でも書いたように、日本の企業のガバナンスは資本主義の原則である所有権(ownership)による支配ではなく、長期的関係にもとづいた会員権(membership)による支配だから、大事なのは組織に忠実で協調性の高いことで、専門的技能は必要ないのだ。
前にも書いたように、日本の大学はシグナリングの装置だから、その役割は入試のとき終わっている。重要なのは「東大卒」の学歴ではなく「東大入学」の能力だから、4年間は遊んでいてもかまわないし、大学の成績も重視されない。仕事は徒弟修行によってOJTで覚えるので、それを習得する文脈的技能が高ければよい。あのつまらない受験勉強を耐えて東大に入った学生は、どんなつまらない仕事も我慢し、上司の求める答を出す忠実な社員になるというシグナルを出しているのである。
だから企業システムを変えないで、教育システムを変えることはできない。企業が汎用サラリーマンを求めているのに、必要もない大学院卒を増やしても、労働市場での価値は上がらない。長期雇用・年功序列システムの特長は、需要の変化に対応して多くの部門に配置転換できる柔軟性なので、へたに博士号をとったりして「専門バカ」になると、つぶしがきかなくて使いにくい。
こうした教育システムが行き詰まっているのは、日本企業の行き詰まりに対応している。かつては市場の変化には配置転換や出向・転籍で対応できたが、情報革命とグローバル化によって変化が急速になり、競争が激しくなると、高度に専門化された企業による水平分業が起こり、サラリーマンでは対抗できなくなる。ところが企業の人事システムは昔のままだから、専門的な判断力のない調整型の経営者が組織内のコンセンサスで経営戦略を決めて失敗を繰り返す。
逆にいうと、学生が専門的技能を生かすには、柔軟な労働市場が必要だ。そのためには、企業が現在のような長期的関係に依存した閉鎖的な共同体ではなく、資本市場で所有権を移転して柔軟に組み替えるモジュールになる必要がある。これはゲーム理論でいうと、繰り返しゲームから戦略的ゲームへの転換である。つまり
- 日本型:会員権―長期的関係―文脈的技能
- 英米型:所有権―労働市場―専門的技能
問題は、1のシステムが長期的に維持可能かどうかということだ。私は、グローバル化の進む世界経済の中でこういうシステムを死守することは、玉砕戦法に等しいと思う。だとすれば、好むと好まざるとにかかわらず、普通の資本主義に移行するしかない。異なる均衡への「パラダイム転換」にともなうリスクや社会的コストはかなり大きいが、それを先送りした結果が「失われた20年」の長期停滞である。
だから教育改革も、産業構造の改革の一環として進めないと失敗を繰り返すだろう。大学進学率が50%を超えた現状では、もう大学はアカデミズムではないので、大部分の私立大学は専門学校と同じように労働市場で即戦力になる人的資源を養成すべきだ。それが離職者の受け皿になれば、柔軟な労働市場を実現して企業システムの改革にもつながるだろう。この意味で、NIRAも提言するように、文科省が経産省や厚労省と連携して、産業政策として大学教育を再建する必要がある。


 日本の経常収支の黒字は、2007年にGDPの4.8%と過去最高を記録した。これは日本の輸出が世界の脅威となった80年代を上回る。当時、前川リポートは「内需拡大」を呼びかけたが、その後も輸出産業に依存する体質は変わらなかった。90年代以降は、国内産業の業績悪化によって輸出への依存度はむしろ高まり、危機前には工業生産の1/3が輸出産業によるものだった。
日本の経常収支の黒字は、2007年にGDPの4.8%と過去最高を記録した。これは日本の輸出が世界の脅威となった80年代を上回る。当時、前川リポートは「内需拡大」を呼びかけたが、その後も輸出産業に依存する体質は変わらなかった。90年代以降は、国内産業の業績悪化によって輸出への依存度はむしろ高まり、危機前には工業生産の1/3が輸出産業によるものだった。 日本企業のR&D投資は高いが、サービス業のR&D比率はアメリカの1/4しかない。通信サービスや旅行代理店など成長の見込める分野も、規制が複雑すぎて外資が入れない。外資が参入した部門の生産性上昇率は平均の1.8倍なので、対内直接投資を拡大することが有効な対策だ。
日本企業のR&D投資は高いが、サービス業のR&D比率はアメリカの1/4しかない。通信サービスや旅行代理店など成長の見込める分野も、規制が複雑すぎて外資が入れない。外資が参入した部門の生産性上昇率は平均の1.8倍なので、対内直接投資を拡大することが有効な対策だ。